
DAW武者修行4日目
誰が言ったか、三日坊主を乗り越えたら希望が見えてくる
どうもどうも!
今朝の鳥雑炊は絶品だったな!
空間移動魔法を覚えたらまたこの山脈にくる、そう約束してオヤジとの別れを惜しんだ。
今日は昨日と一緒でオーケストラ音源についてまた書いてみる。
QLSO Goldを買ってから色々と音色を選んだり、音を鳴らしてだいたいどんな雰囲気なのかが分かってきた。
そこでいよいよ「オーケストラっぽい曲を打ち込んでみるか!」ってなる訳で。
目次
オーケストラ の打ち込みの種類
当然自分はオーケストラのことなんて微塵も知らないわけだ。
で、こういうのは勉強をしたところで無駄に終わる事が多い、なぜならオーケストラの本ってのは「自分がイメージしているものと違う!」これが大きい。
DAWが熟練してきて、色々な曲を作るようになってくると、昔がむしゃらに買った「直伝系」のお勉強本が活きるようになってくる。
買った当初は読んだところでわけ分からん上に、分かってないんだ。
ミックスとかマスタリングの本、アレンジの本とかは特にそうだけど、作曲の後の話になるから、作曲がまだ出来てないのに、これらを読んでも本当の意味で理解出来ない事が多い。てか自分がそうだった (まぁ今も修行中なのだが)
話を戻すと、
オーケストラもまさにそう。自分もオーケストラ関連の本を数冊買って読んだんだけど、自分が知りたいことはそういうことじゃない!って思った。
もうわかったんだけど、自分が欲しい情報は本にはない!って。
本に書いてあることは、再現性がある一般的なことであり、どういう音楽を作るためには、こうやれ、みたいなことが書いてない、というか無理だ。
それこそ自分で作りたのに似てる音楽を聴きまくって研究するしかない。
それらの本に書いてあることは実際には各楽器の音域とか、奏法、対位法とか、ネットでも読めるようなこと。
実際には、各楽器の音域を知ることは必須だし、それらの楽器が一番得意な、かっこよく聞こえる音域をイメージして構成する必要がある。
だけど、最初からそれは出来ない!出来なかった!
そこでだ、自分なりのオーケストラの定義、みたいなものを定める必要があった。
そう、リファレンス・オブ・マイオーケストラ!!
(鳥雑炊が効いているのかテンション上がってきた)
リファレンスとは?

最近だと、OzoneとかのAiによる自動マスタリングで、リファレンス音源を読み込めたりして、自分が理想とする音圧に仕上げてくれる機能があったりする。
それに似ていて、リファレンスとは「参考」って意味。
オーケストラと言われて思いつくのは、クラシック音楽みたいなやつなのか、スーファミでいうオウガバトルのようなゲーム音楽か、ロマンシングサガのようなセンスの良いポップスと融合したような感じなのか、人それぞれ違うんだよね。
で、自分がどういう種類のオーケストラを作りたいか、がまず重要。
これが自分でも分かってないってことは、自分でも何をしているのかが分かっていないのと一緒で・・・
だから最初は数トラックでもいいのでコピーしてるとすごく勉強になる。
私の場合は、ティアリングサーガ、フロンティアゲート、ファイアーエムブレム、ロマンシングサガ、ウィザードリィ、スターオーシャンなどやはりゲーム音楽だった。
そう、全然クラシックのメンデルスゾーンとかじゃな訳で (聞く分には好きだけど)
具体的には覚醒、ミンストレルソング、ディンギル、スタオーなら3、4あたりの作品の質感。ティアリングサーガは相当聴いたし、すごい好きなんだよね。
まずそういう自分が好きなのを洗い出してみる。
すると自分が作ってみたい、って思う質感やクオリティの基準ができるから、求める音源はもちろんんこと、音色を選んだり、音を近づける上でも参考になる。
でもそこまでやんなくても編曲さえ上手くやれれば、音色とかはまだいいと思うんだ。
コピーするわけじゃないんで。
縦と横の表現

オーケストラは色々聴くと表現にかなり幅がある。
いわゆる、縦と横の表現みたいなのがあって、おそらくだけど、DAWで打ち込む場合基本的には「横の表現が苦手」だと思ってて、シンコペーションでフレーズをまたぐことももちろんだけど、独特の揺れみたいなものも必要。
もちろん、各楽器同士のフレーズ自体の絡みも関係してくるし、一番はダイナミクスだったりで、それはもはや作曲する前から計算して構成しないと後からではどうにもならないことが多い気がする。
最近ミックスを真面目に勉強してて思うんだけど、これは曲の作り方の時点でアウトだったな、って感じることがあった。
帯域の成分をどうやって左右中心に配置するか、そういった前提でフレーズや楽器を構成してないから、ではどういった表現だとBGMとして問題なく活きてくるのかって。
逆にバンドのようなテンプレートなサウンドはいいんだけど、ゲーム音楽みたいななんでもあり、って感じの曲の時に気をつけるようにしたい。
話を戻して、
横は無理だと判断して、まず自分は「縦」を意識して作曲してみようと思った。
まぁそもそも苦手云々ではなく、作曲者がそういう表現をしたいか、も関係する。
縦、っていうのは基本的にはクオンタイズするから表現しやすい。
なぜならリズムを指定したグリッドで揃えるからで、これがまさにバンド演奏と打ち込みの違うところだったりする。
逆に言うと、クオンタイズするから生々しくなくなる。
機械的にやったのか、人間が弾いたのかって。
別に弾いてクオンタイズかけなくてもいいし、すこし後からディレイさせてもいい。
ゲーム音楽のオーケストラは打ち込みゆえに、もともとそういう横の表現が苦手だから、逆にいうと、それこそがゲーム音楽らしい、って自分は考えた。
生演奏と打ち込み
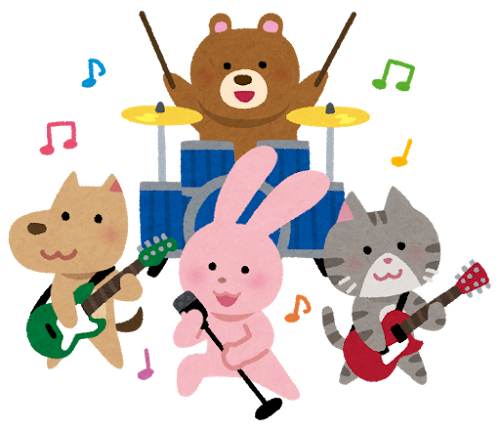
ゲームに音楽の予算かけてそうなビッグタイトルで、さらにオープ二ングなんかだと生演奏で録音されてるものが多い。
最近のゲームの音楽ではわからないから、やはりプレイステーション1、2あたりをまず参考にした方がいいかなって思った。
それでもストリーミング再生も可能になってきたプレステだから、生演奏を録音してDAWとミックスしているような作品もある。
まぁ歌もののオープニングとかはまさにそうだと思う。
ここまで、実際に自分の推測が正しいかどうかは分からない。
ただ、こうやって「自分で考えること」が多分すごく大事だと思っていて、自分が好きな音楽だけでもいいから、CDのライナー見たり、インタビュー探したりして、ヒントを得ていく。
ん!?
「オケオケ山脈、出口まで後20キロ」
あ〜オケオケ山脈ももう少しだなー 20キロって・・・車でもきついぞ
実際にオーケストラ曲を作ってみる
で、御託はいいから早速作ってみようと。
Player Unit
過去にこちらの記事でも書いた曲なので詳しくはそっちを参考に。
基本の型を作って、あとは転調させてBGMとして充実させる、という考えで構成した。
ホルンのかっこいい音域を活かしたいから、空間を作ったんじゃないかな?
it's our turn
SRPGでいうプレイヤーターンをイメージした曲です。
これも縦のラインが揃っている曲で、弦のアルペジオを歯切れよく表現出来てたなって思います。2周目でsus4のアルペジオが対位法で重なるようにしてます。
ブラスのクレッシェンドもリズムを出せるように計算した記憶が。
Edge of the Steel
ウィズのようなダンジョンRPGのオープニングをイメージした曲です。
当時かなり気合いを入れて作った曲で、今聴いても自分が作りたいようなイメージだったんだなーと思う。
ピアノをとにかく組み込もうとしましたね。メロディとか展開がわかりやすいオーケストラを書きたかったんだと思います。
まー失敗の連続で何もかもうまく行かない!!
そこで仕方ないから「影武者メトロノーム」を作成することにした (何それ?)
これは何かと言うと、ずっとリズムをキープしているトラックを作る、すなわち「小太鼓」である。
おいおいメトロノームと何が違うんだ!ってなるんですが、楽器の音でなおかつフレーズでループさせると「雰囲気」が出るんですよね。
無音よりかは、そいつが鳴っててくれていた方が他の楽器を乗せていきやすいって思ったわけです。欠点としては、ちょっとお行儀良い感じになっちゃうところ。
後から部分的に抜いていってもいいし、結構オススメなんです。
これをループさせながら音を重ねていったら上手くいった。
多分人それぞれ上手くいった、マシな感じで作れるようになった、ていう時に何か成功体験のきっかけに鳴る要素があると思うんですよね。
それがこの頃の自分の場合は、影武者メトロノームだった。
反省ももちろんあるんだけど、ピアノ以外は全てQLSOで作ったからだいぶ自分のスタイルがこれで確立出来たのかなーって当時思った。
スタイルっていうのは作り方、構成の仕方、っていう意味ですね。
そこから楽器がどんな感じの質感で、どう鳴るか、っていうのがだいたい分かってきて、他のジャンルの曲を作る時にもその響きが欲しいな、って具合に召喚出来た。
既存の音が欲しい時って、今まで作ってきた曲で鳴っているイメージを思い出して、その記憶から「あの音がこれに合うんじゃないか!?」って感じで呼び出すことが多いです。
ふぅ、ようやく出口か・・・
え!ってか雨降ってきやがったーー!!!!
どこかに雨宿りできるとこねーか!!
ん? ・・・あれは・・・馬小屋か?
サバイバルだ! 手段は選ばねー!!
・・・なんか臭うが仕方ない。雨をしのげるだけで十分だ。
自分なりに完成させることがやはり大事

オーケストラの曲は、なかなか作曲自体を安定させることが難しいですね。
1分のループにしても、かなり各楽器を工夫しないと似たような手法しか思いつかなくなってしまいます。
今もそうなんだけど、自分の場合はどうしてもキーボード的に打ち込んでしまうことが多いんですよね。
まぁそれでも実際の演奏用に編曲し直すとかでもなければ正解はないんで、自由に打ち込んでみるのが最初は大事かと。
苦手な分野とか、やったことない分野の作曲って、手法とか理論とかあってるかどうかなんてどーでもいいから、まずは「自分なりにまとめて完成させることが大事」です。
理論的に間違ってたりしても、メロディとか曲を構成する最低限の要素さえ問題なければ、あとはアレンジの話なんで。
終わりに
個人的には、やっぱりファミコンとかスーファミのリメイク作品がある意味で参考になると思っています。
ドラクエなんかは当然だけど、ポケモンとか、マリオとか、ゼルダとかウィザードリィとかまぁ色々ですね。
リメイクは音楽の三大要素からアレンジを膨らませているので、結局は曲の特徴となってる「メロディとハーモニーとリズムが大事」なんですね。
最低限その3つはトラックでいったら何か、って考えて軸を決めるといいと思います。
つまり、特定のトラックをミュートして、それが消えたら曲が崩壊するみたいなレベルのものがおそらく重要なトラックです。