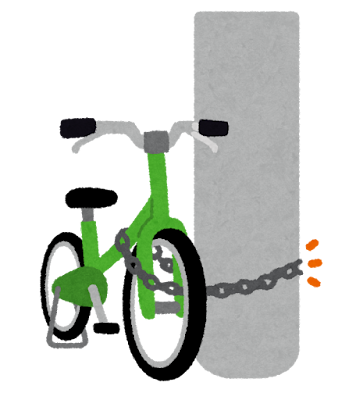
DAW武者修行5日目
山から降りたら急に雨が降ってきて目の前の馬小屋に飛び込むも、そのまま疲れ果てて眠ってしまったのだ。
「!?・・・ここは・・・」
起きたら馬小屋らしき気配は皆無で、何よりも暖かい。
あれ、布団で寝てるぞ。。。どういうことだ?
「あんた、目が覚めたかい。あんなところで寝てたら風邪引くだろ」
「あ、あの、ありがとうございます!」
「その様子だと武者修行といったところか、まぁゆっくりしてけ」
早速今日の本題
音源のことをひたすら書いていくDAW武者修行という企画ですが、今日は音源自体ではなく、「音源/音色と作曲の関係」について持論を述べたいと思う。
音源コンプレックスだった私自身、
音源を理由に曲のクオリティについてあれこれと考えていた時期がありました。
この思考を一旦文字に書き起こして整理して、あわよくば読む人がいるならば巻き添いを・・・
「なぁ兄ちゃん、なんか長くなりそうだな、手短に頼むよ」
「多分無理」
目次
曲と音源の関係

私もそうなんだけど、いつも使ってる音源を取り上げられた瞬間、曲作りが安定しなくなるということが起きる。
安定しない、というのは自分が納得行かないことも含めて。
作曲というのは、基本的にはピアノで弾ける曲、というものを作曲とする場合、コードなりメロディなりが必要になる。
ただ、アンビエントな音色や素材を使って、上物を装飾扱いする曲はその類ではないし、それをピアノで表現しろと言われても無理がある。
なぜなら、音階を使わないと表現できない曲は、環境音に近いものがあるからだ。
鳥のさえずり、波の音をピアノで弾けと言われてもそれは曲ではない。
シンセやFXの効果を利用して使られた音色の曲などもその類。
で、そうなるとメロディやコードやらがきちんとある曲が、音源(のニュアンス)を変えても作ることができる作曲ということになる。
サウンドトラックに例えてしまってるけど、歌もののデモも同じことだと思う。
デモの段階で本気で撃ち込むかどうかは人それぞれだけど、どちらにしても曲が良ければ音源うんぬんなしに見抜く人は見抜くと思うんだ。
それはさておき、
そう言う意味では、作曲なんて、リアルなピアノじゃなくて、スーファミのピアノ音色、でも曲つくりはできるはずなんだ。
原曲の良さを知る
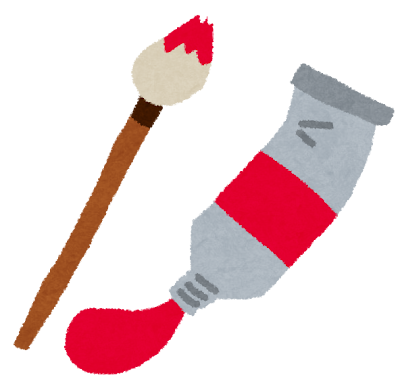
私は音源というのは画家でいうところの「筆や色」だと思ってる。
それが変わると、当然ですがまず「作品の仕上がり」が変わる。
でも、同じ人が書くなら「変わらない部分」ってある、それが「その曲の本質」なんだと思ってる。
曲の良さは音源を変えても出せる。
曲さえよければ。
音色は、どれだけその曲に適したのか、それでその曲の良さをさらにどこまで引き出せるか、だと思ってて。
そして、それには「アレンジ」が関係してくる。
わかりやすく言うと、
ドラクエの序曲がある。
これはファミコン音源でもみんな良いって思う(思うんだよ)
で、スーファミの音源でもさらに具体的になって良い。
本当のオーケストラで演奏されても最高。
ピアノで弾いても良いわけ。
なぜかって、原曲が良いから。
多分どんな曲でも売れた曲や人気がある曲は、着メロでも良い曲なんだ。
原曲とアレンジ

先ほどの話だと、
オーケストラで書いた曲が原曲、と言う扱いにすれば、それがよければファミコンにアレンジしても良い曲なわけ。
今は音源がリアルになっていけば、と言う視点で書きましたが、逆もありうるわけで。
オーケストラで書かれた曲を原曲とする場合、ピアノでアレンジして賞賛を浴びることもある。
でももともと曲が良くなければ、ピアノで弾いても良さは伝わらない。
つまり、曲の良さは作った時点で、仮に基準値として50で固定されていて、
51-100は音色やアレンジ次第でさらに良くなる可能性がある「期待値」と言うこと。
ついでに言ってしまうと、使われる作品やシーンにマッチしているか、ユーザーの好みも期待値に追加されるんじゃないかな。
だから音源も基本的に良いものを使えば期待値が上がりそうだから、もっと良くなる!ってなると思うんだ。
でも、その前提に当然として「原曲が良い」って言う条件がある。
あくまで相乗効果なのか、迫力でごまかしているのか。
基本的に聴く人は、音圧が大きかったり、音がリアルだとかっこいいと感じると思う。確かにそれは音楽作ってても思うし。
迫力でごまかせるなら、むしろそれはラッキーだとは思うけど、まぁそれも含めて自分でよく考えたいこと。
それを忘れない為に、脳内で音源をチープにしても聴くに堪える曲なのかを常に意識することも大事だと思うんだ。
私なら、この曲ファミコンとかゲームボーイ、スーファミで表現したとしても聞けるような曲なのかなーって (またゲームか)
だから、作った曲で音源について悩む場合、それはあくまで期待値なのか、曲そのものの本質、核である部分が問われるレベルなのかを考えたい。
そうすると、だいぶ自分が買うべき音源を絞れると思うんだよね。
コスパの良いものを追加していけると言うか。
そのために、やっぱり手持ちの音源を見直す必要もあると思うだ(自戒を込めてw)
音源も含めて評価する人たち

もちろん、音色の良さも含めて原曲として評価とする場合がある。
こればっかりは、聴く人次第。
先ほど基準値とか、期待値とかって言ったけど、そんな事普通考えて聴いてないので、単純に点数は合算で考える。
その曲が色々含めてドストライクだったのかどうか。
音のリアルさとか、作品にマッチングしているか、ってレベルまで考えて聞き分けて評価するかどうかの話で。
多分、音楽やってる人とか、音楽ファン、特定の楽器プレイヤー。。
自分がそれ含めて、どう受け取られたいか、だと思う。
でもその部分こそが、逆に今度は「自分が誰かの曲を聴いた時、どこが良いと思うか」ってところだと思うんだよね。
だから曲聞いて
「このピアノの音がかっこいい!」
とかって思ったら、その音が例えチープになっても、その曲の良さは変わらないのか、とか考えることが、自分にとっての曲の良さを考えることだと思う (音源の面で)
もし変わらなければ、その音やフレーズは本質を備えている、と言うことになる。
ダメなら、音色でごまかしている、あるいは音色の力が相当に強く働いている、と言うこと。
本質的に、そのリアルさじゃ無いと曲の表現として成り立たないなら「基準値」
あくまで相乗効果の話なら「期待値」
それは買う音源を選ぶときにも考えたいこと
仮に表現力が10段階あるとして、
それを買えば、1→7になるのか、7→9になるのかということ。
7→9は音楽やってるか、その楽器プレーヤーしか聞き分けられない領域かもしれません。ならば1→5、6、7、になるようにする方が重要だと思うんだ。
先ほども書いた通り、聴く人の解釈や好み、作品にマッチングしているかどうか、も影響してくるので、曲の評価というのはより複雑になってく。
ゲーム内で聴きまくって、ゲーム自体も良かったから曲もいい、っていう効果と一緒。
その中でも、音源というものは、どこまで聴く人にとって曲の評価を左右する存在なんだろうか、という。
「兄ちゃん、まだ続くんか?」
「もうちょっと」
作曲者とユーザーの間にあるもの
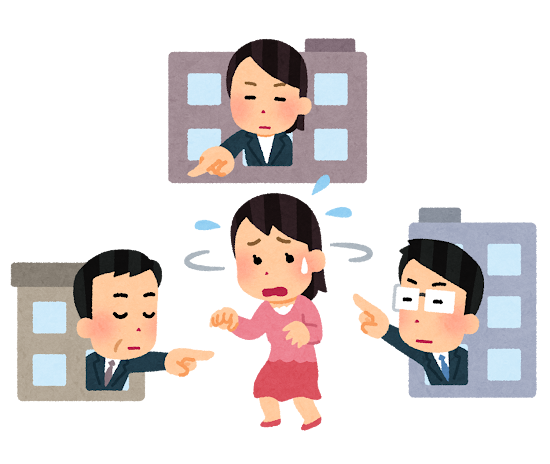
「まぁ飯でも食えや、ほら、シャケご飯だ、うまいぞ」
「うま!!」
話を戻す、
今度は自分が聞く側になって考える。
自分が既製品の楽曲を聴いていて「ここがこうだったらもっと良いんだけどなぁ」って言う部分があると思うんだよね。
(まぁ大抵は、作れらたものを受け入れるだけど)
例えば、
もう少しスネアの音が出ていたら・・・
もう少しリバーブがかかっていたら・・・
もっとストリングスがリアルだったら・・・
色々あると思う。
原曲でも言えることだけど、もしかしたら既存曲を他のアレンジャーがリメイクした場合でも、ミックスとか音源が変わる。
その時に、原曲と比べるわけで。
良い部分もあれば、好みでない部分もある。
でも、原曲の良さはやっぱり固定値なんだ。
そして聴く人の期待値がある。
例えば、原曲に対してアレンジアルバムがあるけど。
でも、アレンジアルバムなのに、原曲とほとんど一緒やんけ!って評価下げる人がいる。
それはアレンジアルバムとして期待したのに、原曲とあまり変わってないから期待値が伸びないんだ。51-100の部分。
これも曲の評価の仕方が違う例だと思う。
ゲームのリメイクで例える

で、これってゲームに例えると面白くて。
聴く人によっては、リメイクから入る人もいるわけで。
FFとかはリメイクが何度も行われていますが、私のような昔から知ってるユーザーは最近のグラフィックや表現などに対して、やはり原作を始点に評価してしまうわけ。
でも、今の若い人たちで原作を知らない人たちは、リメイクから入るわけで、それで違和感ないんだよねきっと (そういう声もあるという話)
それは曲も一緒。
ゲーム自体が面白いから、多少グラフィックなどが変わっても面白いわけで。
その時、私たちは最近のリメイクをみて「原作のどこが良かったから、良いと思ったんだろう」って考えるんだよね。
ゲームというものは音楽に比べると、構成されている要素がとても多い。
だから面白さを特定させることは難しく、それこそユーザーの属性次第。
話が大きくなって本題から逸れちゃってるけど、音楽という単品で考えるのか、音楽は素材としての役割で考えるのかでも評価は変わるということ。
その点で、音源の立ち位置を考えていきたいわけなんだよね。
ゲームに話を戻して、
やはり天野さんの絵の世界観なのか、シナリオなのか、システムなのか、ゲームバランスなのか、キャラクターなのか。
それを考えると、グラフィックが多少変わっただけでは別に原作の良さはグラつかないわけで。楽器の音色が少しよくなった悪くなったと似ている。
ただし、グラフィックが命!とか言ってそのゲームを評価してた人は、一気にクソゲー扱いになる。だってそれ命だったわけなので
「そんな極端な奴がいるんかよ」
「まぁ多少はいるでしょう」
それよりも、バグとか、操作性とか、そういった部分も当たり前だけどかなり大事だったんだなーとかわかる。違和感なくプレイできることがまず大事。
曲も違和感なく聞けることができれば、細かい部分は作曲者しか聴いてないような部分だったりするわけで。
それよか違和感なく聞かせるには、音源をよくするとかより展開とかメロディとかミックスが重要。
逆に、グラフィックだけどんどん豪華になって内容はつまらない!
って言ってるユーザーも一定数でいるわけ。
それって、音楽で例えたら、音源だけ良くなってくけど、曲自体はあんまり良くない、ってのと似てないかな?
グラフィックが昔のレトロゲームでも面白い、ってのと似てるんだ。
だから「何が〜だから、面白いんだろう、良いんだろう?」って常に考えるの大事なんだよね。
「うまく話戻したな」
「あぶねー」
かっこいい部分を自分で説明する

「風呂湧いたぜ、入ってくる?ついでに話をもう終わらせてほしいんだが」
「もう少し」
それらを踏まえると、
結局は自分が「曲の良い部分、かっこいいと感じられる部分はどこなのかをまず考えてみる」と言うこと。
つまり、今悩んでる部分が、固定値なのか期待値なのか。
何かの作品やゲームのために作っている曲なら曲単体で考えてもダメなんで。
曲の良さ、というのは作曲者による解釈とユーザーによる解釈がある。
作曲者は音源が曲の良さに影響する、って思っているかもしれないけど、ユーザーからすれば、曲がシーンにあっているかどうか、メロディの良さ、もしかしたらトレンドの方を重視しているかもしれない。
すると、音源がどうとか、っていう考えはあくまで自分視点なだけなので、他人からしたら大した変化ではない、という。
もちろん、先ほどの1→5の話か、5→7,8の事も絡めて。
「兄ちゃん、いいから風呂入れ」
「だいぶ頭の中がスッキリしました」
「1時間くらい出てくんじゃねーぞ、なんなら風呂で続きを一人で呟いてもいいぞ」
「いや、5分で上がります」
「・・・」
終わりに
音源がなぜ魅力なのか!?
それは、音源を買う、という事が多分
作曲者からすれば「一番曲作るときに変化を感じれる部分」だからだと思うんだよね。
つまり、早く結果や効果が出る、ということ。
ただその反面、音源がどこまで良い、悪い、という基準は決まってない訳で。
なぜなら、
それは聴く人がどこまでそれに対して知識があるかで左右される、からで。
スーファミ好きな人ならスーファミ音源を理解できるけど、知らない人は「昔の音みたい」っていう感想で終わりなんだ。
懐かしいな、いいな〜という声もあれば、音がなんか昔っぽいね、って。
だからファミコン音源や、スーファミ音源で作ると勉強になったり。
結局は、自分の価値観に共感してくれる人と繋がっていく、それが人生だと思う。
その中で音源の良さや、価値ってなんだろうって。
「兄ちゃん、まだ呟いてんのか」
「止まんないっす」
「5000文字超えたぞ」
DAW武者修行は続く
(決して一人で部屋で呟いているわけでは無い)